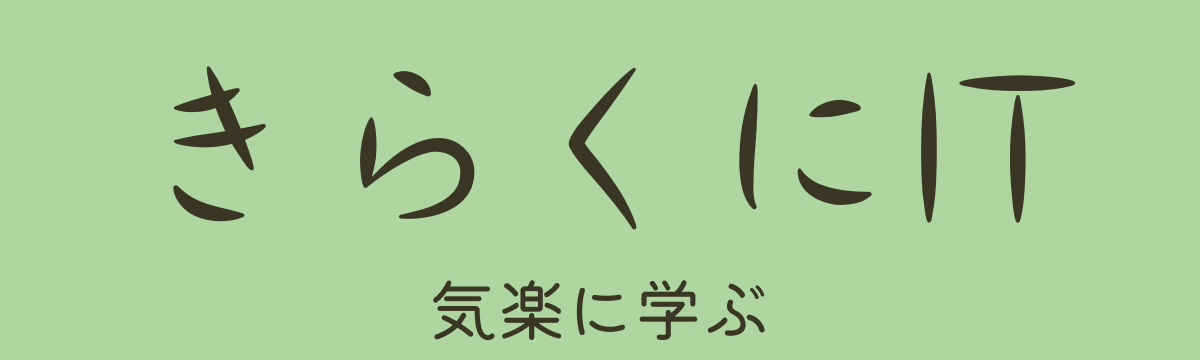最近、Webサービスの運用をしていると頻繁に耳にするようになった「ブルーグリーンデプロイメント」という言葉。なんだかカラフルな名前で覚えやすいけれど、実際にどのような仕組みで動いているか、そしてどんなメリットがあるのかをちゃんと理解していますか?今回は、そんなブルーグリーンデプロイメントについて、その仕組みやメリット、そして実際に運用する際の注意点までわかりやすく解説していきます。
ブルーグリーンデプロイメントとは何か?

ブルーグリーンデプロイメントとは、システムのアップデートや変更を安全に行うためのデプロイ戦略の一つです。簡単に言うと、古いバージョン(ブルー)と新しいバージョン(グリーン)の2つの環境を用意し、瞬時に切り替えられるようにする手法です。
例えば、あなたの運営しているWebサイトがあるとします。現在公開中のバージョンを「ブルー環境」、新しいアップデートを適用した未公開の環境を「グリーン環境」とします。ユーザーは常にブルー環境にアクセスしていますが、テストを十分に終えた後に、グリーン環境に瞬時に切り替えることで、ダウンタイムなしでスムーズなアップデートを実現できます。
ブルーグリーンデプロイメントの仕組みを具体的に理解しよう
それでは、具体的にブルーグリーンデプロイメントがどのような仕組みで動作するのか、順番に説明していきます。
① 2つの完全な環境を用意する
まず、同じ設定を持つ2つの完全な環境(ブルーとグリーン)を準備します。データベースやサーバーの設定も全く同じ状態になるようにします。これが基本的な前提条件です。
② 新バージョンのデプロイ
次に、現在公開中の環境(ブルー環境)とは別に、新しいコードや機能をグリーン環境にデプロイします。この段階ではまだユーザーには影響がありません。
③ グリーン環境のテスト
グリーン環境で徹底的なテストを実施します。ここでバグやエラーがあれば修正し、動作が安定するまで調整します。この時点ではブルー環境がユーザーからのトラフィックを処理しているので、グリーン環境のテストをゆっくりと、念入りに行うことができます。
④ トラフィックの切り替え
テストが終了したら、ルーティングを切り替えてユーザーのトラフィックをグリーン環境へ流します。切り替えはロードバランサやDNS設定などを変更することで簡単に実行できます。これによりユーザーは瞬時に新しい環境へと移ります。
⑤ 旧環境(ブルー環境)をバックアップ
切り替えが完了して新環境での動作が安定したことを確認したら、旧環境であるブルー環境は一定期間バックアップとして保持しておきます。万が一、新環境で問題が発生した場合でも、すぐに旧環境に戻すことでリスクを最小限に抑えられます。
ブルーグリーンデプロイメントのメリット
ブルーグリーンデプロイメントの大きなメリットについて詳しく見ていきましょう。
① ダウンタイムがほぼゼロ
デプロイに伴うダウンタイムがほぼありません。ユーザーにとってサイトが止まるというストレスがなくなるので、サービスの品質が向上します。
② リスクの軽減
新しい環境での問題が発生した場合でも即座に旧環境に戻すことができるため、大きな障害を未然に防げます。これにより、アップデートが頻繁なアジャイル開発やCI/CD(継続的インテグレーション/デリバリー)とも相性が良く、安心して積極的な開発が可能になります。
③ 安全で容易なロールバック
トラフィック切り替え方式なので、新環境に問題が見つかっても即座に元の環境に戻せます。ロールバックに時間がかからないため、サービスへの影響を最小限に抑えることが可能です。
ブルーグリーンデプロイメントの課題と注意点
もちろん、ブルーグリーンデプロイメントには注意すべきポイントもあります。
① コストが高くなる可能性
2つの完全な環境を維持するため、インフラコストが増加する可能性があります。クラウドサービスを利用する際には特に、このコストを考慮する必要があります。
② データベースの同期
データベースの同期が必要なサービスの場合、ブルーグリーンデプロイメントは複雑になります。データベースのマイグレーションが必要になるケースでは特に注意が必要です。
実際にブルーグリーンデプロイメントを導入するには?
AWS、Google Cloud、Azureといった主要クラウドサービスにはブルーグリーンデプロイメントを容易に実現できる機能が備わっています。例えばAWSなら「CodeDeploy」や「Elastic Beanstalk」を利用することで簡単に導入可能です。インフラの自動化ツールとしてTerraformを使用して環境の作成と管理を効率化するのもおすすめです。
まとめ

ブルーグリーンデプロイメントは、サービスの安定運用や開発効率の向上を目指す上で非常に有効な戦略です。ダウンタイムを最小限に抑え、ユーザー体験を向上させることで、サービスの信頼性も高まります。クラウド時代の今だからこそ、この手法の導入を検討してみてはいかがでしょうか?
きらくにITでも、こうした最新のインフラ運用のテクニックを随時ご紹介していきますので、ぜひこれからもお楽しみに!