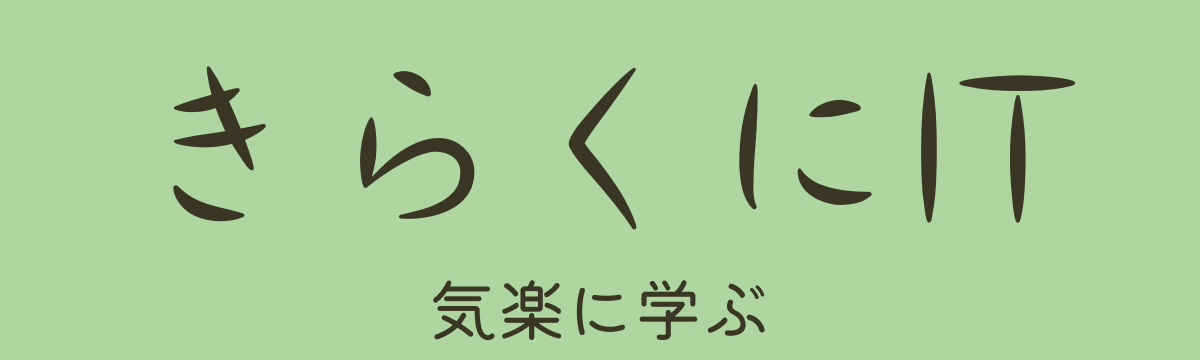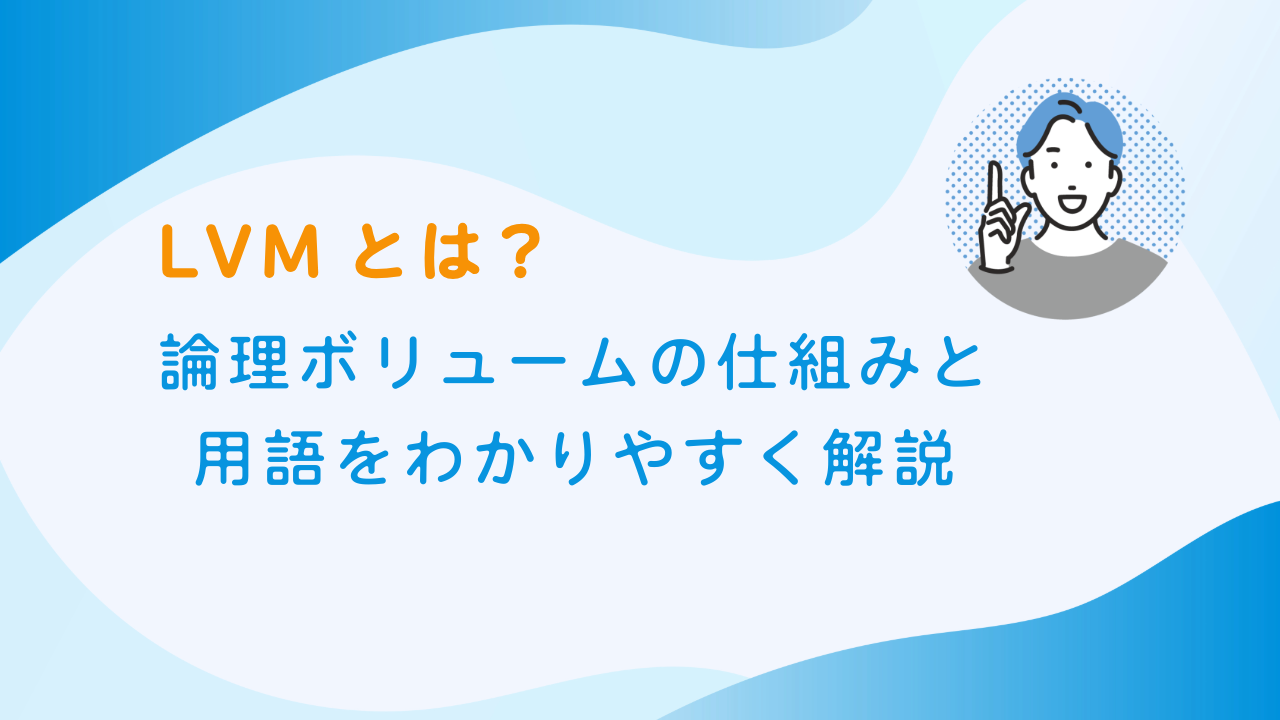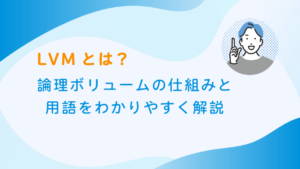Linuxでサーバーを運用していると、「ディスクの容量が足りなくなった」「新しいストレージを追加したい」といった場面に出くわすことがあります。
そんなとき、柔軟にディスクを管理できる便利な仕組みが「LVM(Logical Volume Manager)」です。
この記事では、LVMの基本概念から、仕組み、よく出てくる用語、そして実際にどんな場面で役立つのかまでを、初心者でも理解できるようにわかりやすく解説していきます。
LVMとは何か?

LVMとは「Logical Volume Manager(論理ボリュームマネージャ)」の略で、Linuxのディスク管理を柔軟に行うための仕組みです。
通常、ディスクのパーティション(領域)は物理的に固定されています。
たとえば、HDDを「Cドライブ」「Dドライブ」と分けた場合、後からサイズを変えるのは簡単ではありません。
しかしLVMを使うと、物理的なディスクの制約にとらわれず、論理的にディスク領域を拡張・縮小・統合できるようになります。
つまり、「システムを止めずに容量を増やす」「複数ディスクを1つの領域として扱う」といったことが可能になります。
LVMが使われる主な理由
LVMがよく使われるのは、特にサーバーやクラウド環境など「可用性」と「柔軟性」が求められる場面です。
具体的にどんなメリットがあるのかを見てみましょう。
1. 容量の拡張が簡単
LVMを使えば、サーバーを停止せずにディスク容量を追加できます。
新しい物理ディスクを接続しても、既存のボリュームにそのまま組み込めるため、容量不足への対応がスムーズです。
2. 複数ディスクを1つの領域にまとめられる
通常は1つのディスク=1つの領域という考え方ですが、LVMを使えば複数のディスクを束ねて「1つの大きなストレージ」として扱えます。
たとえば、500GB×2枚のディスクをまとめて1TBの領域にすることも可能です。
3. スナップショットの作成
LVMには「スナップショット」という機能があります。
これは、特定時点のディスク状態を保存する仕組みで、バックアップや検証にとても役立ちます。
万が一トラブルがあっても、スナップショットを利用してすぐに元の状態に戻せます。
LVMの基本構造を理解しよう
LVMを理解するためには、登場する3つの主要な要素を押さえておくことが大切です。
| 用語 | 説明 |
|---|---|
| PV(Physical Volume) | 実際の物理ディスクやパーティションを指す |
| VG(Volume Group) | 複数のPVをまとめたグループ |
| LV(Logical Volume) | VGから作られる仮想的な領域(ファイルシステムを作る場所) |
この3つがLVMの中核です。
それぞれをもう少し具体的に見てみましょう。
1. PV(Physical Volume)とは
PVはLVMで管理される「物理的なストレージ単位」です。
HDDやSSD、もしくはその中のパーティションをLVM用に初期化するとPVになります。
例えるなら、「LVMの世界に登録されたディスク」というイメージです。
2. VG(Volume Group)とは
VGは、複数のPVを束ねた「ストレージのプール(貯水池)」のようなものです。
たとえば、2台の500GBディスクを1つのVGにまとめれば、1TBのVGが作れます。
VGはあくまで「まとめた領域」なので、まだ実際に使うファイルシステムは存在しません。
この中から必要な分だけ切り出して使うのが次のLVです。
3. LV(Logical Volume)とは
LVはVGの中から作る「実際にファイルシステムを作成して使う領域」です。
つまり、ユーザーやアプリケーションから見れば「ディスクドライブ」として認識される部分です。
LVのサイズを後から拡張したり、縮小したりできるのがLVMの大きな強みです。
まとめるとこうなる(イメージ図)
┌────────────────────────┐
│ VG(Volume Group) │← 複数PVを束ねた大きな器
│ ┌──────┬──────┐ │
│ │ PV1 │ PV2 │ │ │ ← 物理ディスク
│ └──────┴──────┘ │
│ ┌────┬────┬────┐ │
│ │ LV1 │ LV2 │ LV3 │ ← 論理的な領域
│ └────┴────┴────┘ │
└────────────────────────┘
このように、LVMでは「物理 → グループ → 論理」の3層構造になっており、
それぞれが柔軟に拡張・統合できるのが特徴です。
仕組みをもう少し掘り下げる
LVMは、VGの中で「物理エクステント(PE)」という小さな単位でデータを管理しています。
これはディスクの最小ブロックのようなもので、通常は4MBや8MBといったサイズです。
VGを構成するPVも、同じサイズのPEに分割されます。
LVを作るときは、このPEを必要な数だけ割り当てることで容量が決まります。
たとえば、PEサイズが4MBで1000個のPEを割り当てた場合、
LVの容量は「4MB × 1000 = 約4GB」となるわけです。
この仕組みにより、LVを動的に拡張できるようになっています。
新しいディスク(PV)をVGに追加すれば、空きPEが増えるため、既存LVのサイズを大きくできます。
LVMの代表的な機能
ここでは、LVMを使う上で特に便利な機能を紹介します。
1. スナップショット
スナップショットを使うと、現在のボリュームの状態を一時的に保存できます。
たとえば、バックアップを取る前にスナップショットを作成すれば、バックアップ中にデータが変更されても問題ありません。
万が一のトラブル時にも、スナップショットをもとにすぐ復元が可能です。
2. ボリュームの拡張・縮小
LVMではLVを後から拡張したり縮小したりできます。
たとえば、Webアプリのデータ量が増えたときでも、システムを停止せずに容量を増やせるのは大きな利点です。
3. ミラーリング(RAIDのような機能)
LVMには、データを複製して保持する「ミラーリング機能」もあります。
これにより、1つのディスクが故障しても、もう一方のディスクからデータを読み込むことができ、信頼性が向上します。
LVMの弱点・注意点

便利なLVMにも注意点はあります。導入前に以下の点を理解しておくと安心です。
- 構成が複雑 通常のパーティションよりも仕組みが複雑なので、設定ミスがトラブルの原因になることがあります。
- スナップショットは万能ではない スナップショットは便利ですが、容量を消費します。長期間保持するのには向いていません。
- トラブル時の復旧が難しい LVM特有の構造を理解していないと、万一の障害時に復旧が難しくなる場合があります。 そのため、バックアップは別途しっかり取ることが推奨されます。
LVMが活躍するシーン
- サーバーのディスク容量を後から増やしたい
- データベースやログ領域の急な拡張に対応したい
- 仮想環境(KVMなど)で柔軟なストレージ管理をしたい
- バックアップやテスト用にスナップショットを取りたい
このように、LVMは動的なシステム運用を求める場面で特に力を発揮します。
一問一答(簡単まとめ)
- LVMって初心者にも必要?
-
個人PCでは不要な場合もありますが、サーバーやクラウドでは非常に役立ちます。
- LVMとRAIDの違いは?
-
RAIDはデータの冗長化や高速化を目的としますが、LVMは容量の柔軟な管理が目的です。両方を組み合わせることも可能です。
- スナップショットはバックアップの代わりになる?
-
一時的なバックアップには使えますが、恒久的なバックアップとしては別管理が必要です。
- LVMの設定を間違えると?
-
データ損失のリスクがあるため、操作前にバックアップを取るのが基本です。
まとめ:LVMは「柔軟なディスク管理」を実現する仕組み
LVMは、従来の固定的なディスク構成に比べて圧倒的に柔軟です。
サーバーの容量を簡単に増やせる、バックアップが取りやすい、ストレージを統合できるなど、現代の運用環境に欠かせない技術と言えます。
特に、クラウドや仮想化が当たり前になった今、
LVMの理解はLinuxを扱うなら知っておくと便利なことの1つです(エンジニア等に限るかも)。
今後サーバー構築やシステム運用に携わる予定がある方は、
ぜひLVMの基本概念を押さえておきましょー