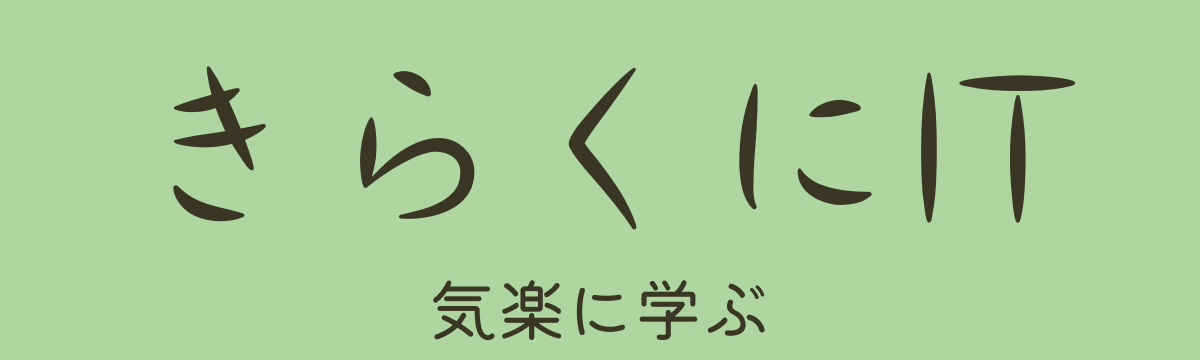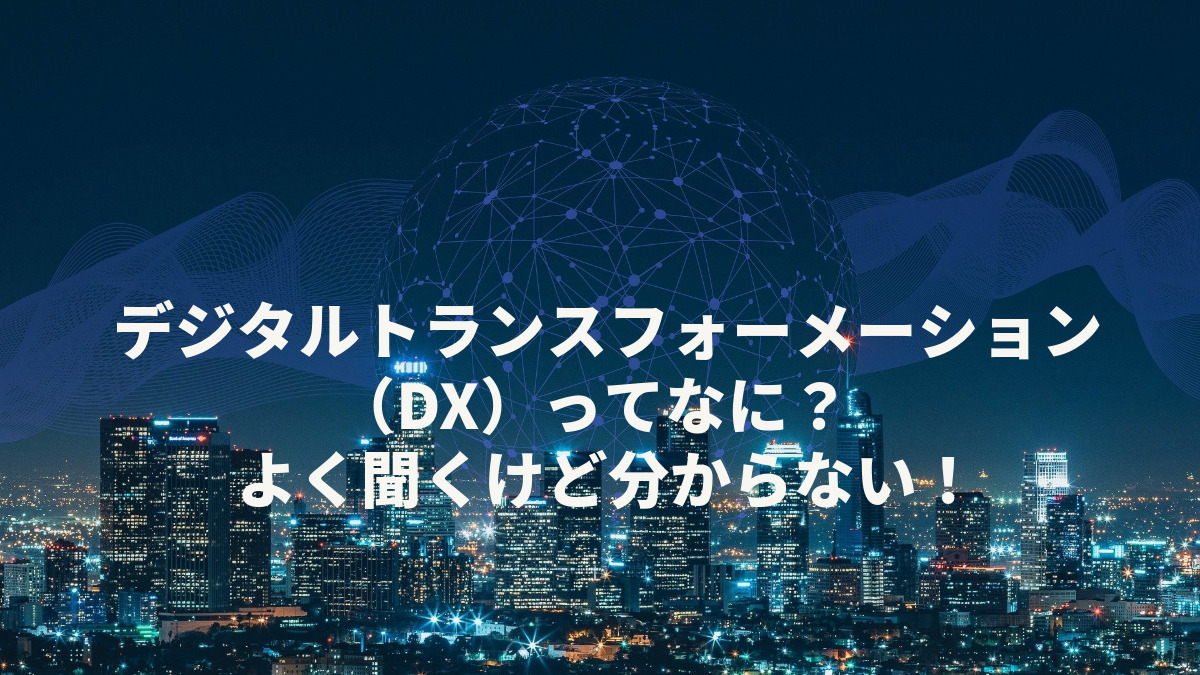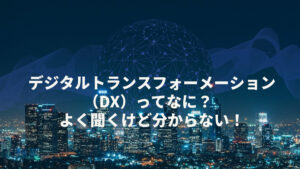コロナ禍もあり、DXを進める加速が早くなっています。
それとともに、DXのメリットに着目し相次いで導入する企業も増えています。
今やなくてはならない存在になってきているDXですが、DXについて基本的なことや進め方なども含めご紹介していきます。
そもそもDXとは

DXとは「Digital Transformation(デジタルトランスフォーメーション) 」の略称です。
直訳は、「デジタル変革」で、意味としてはAIやIoTなどのIT技術をまだ利用していない企業などに導入してより効率化をすることを指します。
企業だけでなく、行政など社会的にもDXを進めるようになりました。
2004年にスウェーデンのウメオ大学のエリック・ストルターマン教授がDXという言葉の生みの親とされています。
教授自身は、IT技術が人々に浸透させることで良い方向へ変化させると考えています。
DXとIT化の違い
DXとIT化は厳格な違いがあるわけではない
むしろIT化とデジタル化が同じように使われるようになりました。
ただ、DXとIT化はそれぞれの目的が違う
簡単にいうとIT化は戦術で、DXは戦略
IT化は業務の効率化を主な目的としています。
ノートに計算して帳簿を書いていたものが、パソコンの会計ソフトで計算も帳簿もできるようになり、結果作業時間が短縮されるとIT化による効率化となる
業務内容は基本的に変わらないがIT技術を使うことにより生産性が向上することをIT化となる
DXは、先ほどの会計ソフトを取り入れるだけでなく、企業などでいろいろなIT化を進めて全体的にIT化を進めて業務が圧倒的に変わっていき、これが組織の変革になっていくことを指します。
つまりIT化を進めていくことで企業の在り方が変わる、リモートワークなどの働き方が変わっていくことがDXと言える
また、IT化は社内ユーザーを対象にしているのに対し、DXは社内だけでなく顧客も含めた社外関係者も対象に含まれる
顧客に対してのサービスもIT化を進めることで利便性が向上するなどで初めてDXと言える
DXの進め方(例)・事例
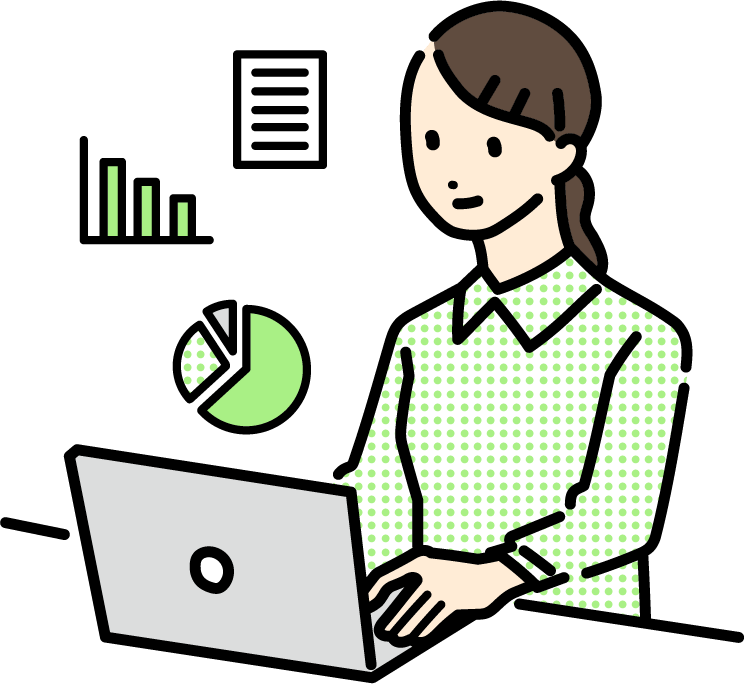
ステップ1:DX度合いの把握
どのくらいDXを行われているのか調査します。
DXが行われていないかだけでなく、課題も見つけます。
ステップ2:目標を立てる
どんなところどんな風にDXを行うのか目標を立てます。
DXを行った後にどのような状況になるかまで目標を立てると無駄やDXの力を最大限引き出すことができます。
できれば、社員が複数いる会社の場合は経営者が率先してDXを進めていく姿勢を示し、DXに対して理解と協力を得ることは不可欠です。
例え、DXで失敗したとしてもそこでDXが終わらないように、何度もチャレンジできる環境を整えることでよりDX化を進めることができるでしょう。
逆に、経営者など重要な役職につく方の理解を得られないことも考えられます。
しっかりとDX化のメリットを提示し、説得できるようなデータなどの提示も必須です。
場合によって組織自体が大きく変わることも考えられるので慎重に進めていくことも考えられます。
また、DXを進めていくことでいろいろなシステムを入れることで、費用が嵩むことも考えられます。
情報の共有もうまくいかなくなる可能性もありますので、少しずつ進めていくことも考えにあると良いでしょう。
ステップ3:人材確保と実行
DXを行う目標を立てれば、あとはDXを行うために人材確保をします。
データなのか、デザインなのか、エンジニアなのか適材適所の人材を確保し、DXを進めていきます。
この際に、人材を育成したり、研修も検討の範囲に入れましょう。
人材が確保できないうちに実行してしまうとうまくDXが進まない可能性があります。
しかし、人材不足でもあるため、人材を確保するために会社の環境や待遇を良くするなども場合によっては必要でしょう。
DXの導入事例
DXの導入事例は様々ありますが、ここではいくつか挙げておきます。
・受付をチャットボットやAIで対応
・注文を全てタブレットで行い、決済もキャッシュレス決済で行う
・在庫確認をバーコードで行う
・農業だと畑などの管理を衛星からAIが判断して病気を見つるなど、畑の状況を細かく把握しやすくなる
DXの凄さ・メリット
生産性の向上
DXのメリットとして大きく貢献すると言われているのが生産性の向上です。
結果的に、業務の自動化や無駄な作業の削減につながることで、集中しなければいけない業務に集中したり、コストを削減することも可能です。
新サービス、新ビジネスの開発ができる
IoTの商品からユーザーの使用データをとり、今後の商品開発の情報を取得し、分析・活用することで新サービスや新ビジネスの開発も可能です。
また、AIを利用することで画像・音声認識などが可能になり、そこからまた派生して新サービス、新ビジネスが生まれています。
緊急事態にも対応できる
自然災害などにより業務が止まってしまう可能性もあります。
例えば、自然災害であれば外出できずとも通信と電源確保ができれば自宅からでも他の地域からでも仕事をすることもできます。
実際にコロナ禍では外出することを控える時期がありましたが、テレワークによりビジネスの存続をできる企業も多かったことでしょう。
DXの壁

DXを行うことでよくセットのような形で言われているのがDXがうまく進まない、「DXの壁」などと言われます。
具体的にDXを行うのになぜ進まないのか、進めることができないのかをここからはご紹介します。
費用がかかる
DXはシステムを変えることになります。
今までアナログでやっていたものなど効率化を図るためデジタルなツールなどを使い、業務を方法を変えてしまいます。
無料で変えられるツールというのはほとんどなく、ITのツールを変えるだけでお金がかかったり、維持費がかかる可能性があります。
将来的に見れば結果効率も良く、全体的なコストが抑えられるのですが、なかなか最初の方は納得がいかないことがあるでしょう。
DXに積極的でない
教育でもパソコンについて学び始めたのはつい最近です。
年齢層が高くなればなるほどITへの抵抗感が高い可能性があります。
実際に、スマホの普及率が高いものの、だからと言って皆全てが得意というわけではありません。
そのため、DXをしてもなかなか業務が進みづらかったり、今の業務を辞めたいという方も少なくないでしょう。
また、DXにしたからといって必ず利益が上がるわけではありません。
DXで業務がスムーズに行われても費用を削減できたり、利益を上げることをしなければ意味がありません。
さらに、大幅なコスト削減など何か大きい成果が見えなければ経営層も首を縦にふる可能性が低くなります。
そして、DXについて知識が乏しかったり、人材が不足しているだけでもDXを進められるのか難しくなります。
人材だけを揃えてもうまくいかなければ責任が付きまといますし、知識が乏しいとDXがうまくいかないだけでなく、費用と時間がかかり結果無駄なことをしてしまう可能性もあります。
特に日本はアジアでもDXが遅れている国でもあり、DXが進んできたものの中小企業などを中心にまだまだ進んでいないところが多いです。
その中でDXを進めること自体が難しい環境でもあります。
DXの連携が難しい
会社であれば社内だけでもDXの連携が難しかったり、社外でも取引先とのやりとりが難しい可能性も出てきます。
今までのシステムと連携することが困難な可能性もあり、なかなかDXが進まない可能性があります。
まとめ
DXを進めれるのであれば進めた方が良いでしょう。
しかし、ただDXするというだけでは逆に非効率になってしまいかねません。
DXありきの推進ではなく、企業であれば課題に合わせたDXを考えることの方が効率的で生産性も上がるでしょう。
DXはなかなか進みづらい可能性もありますが、いろいろな人に興味を持ってもらえるだけで少しでも円滑にDXを進められるかもしれません。
また、今回少しでも、言葉の意味を知って、興味を持ってDX化について相談してみたいという方、お問合せにてお待ちしております!!